

ぐるりと北海道 −北の秘湯を駆け足の旅−
目 次
まえがき−夜のサッポロ−丸駒温泉−雷電朝日温泉−神威岬−小樽にて
留萌−天塩から宗谷岬−宗谷岬−オホーツク海に沿って−知床半島で
ウトロからラウスへ−根室岬より弟子屈へ−オンネトーと然別湖−
幌加温泉−黒岳へ登る−
夜の藻岩山からサッポロの市街を眺めるとまるで宝石箱をぶちまけたよう
で光が乱舞している。光が途切れて暗いところが北大のキャンパスらしい。
中山峠へ向かうライトが光のくさりになって美しい。展望台は、秋めいた夜
の風が吹いている。
丸駒の露天風呂の湯は、ややぬるくてなめらかである。周囲の岩がつるつる
して滑り易い。眼の前を支笏湖の遊覧船が通って行く。虻を追いかけながら
こちらからも眺めている。
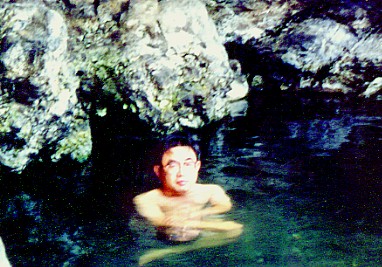
雷電海岸は秘境である。山脈が大海になだれ込んで波打ち際の一線をか
ぼそく道路が走っている。日本海の海鳴りが荒々しく聴こえる宿の一夜を
過ごした。

カムイ岬は車を降りてから随分歩かなければならない。終わりは馬の背の
ように両側から海が迫っている。その先に灯台がある。岬の果ては海が天
空に溶け込んで茫々としている。足元の砂が熱い。

サロベツ原野の端を日本海が洗っている。浜は流木が打ちあげられて荒
涼たる風景である。遙か彼方に半分は雲に覆われた利尻富士が浮かんで
見える。
日本最北端の岬が宗谷岬である。小高い丘に旧海軍の望楼があり、明治
の昔バルチック艦隊が通過しないか見守っていたそうである。売店のスピー
カーが「ハマナス揺れる宗谷の岬 」と がなりたてている。

ウトロ港には、森繁久弥の「知床旅情」の碑がたっている。オホーツク海は
波もなく、港につながれている知床観光船も灯りをすべて消してわずかに
揺れている。

ラウスに近い熊の湯の露天風呂は、国道から川を隔てた向こう側にある。
簡単な脱衣所はあるが、入湯料は無料で近くのキャンプ場からの学生らが
入りに来ている。湯につかりながら聴くせせらぎの音は格別である。
 知床峠、背景は羅臼岳
知床峠、背景は羅臼岳
幌平から層雲峡へ向かう国道の脇に幌加温泉がある。療養の湯で、午後
七時には宿泊客はすべて就寝する。虫が多くて浴室は閉めきっているが、
暑いので少し窓を開けるとすぐ虫が飛び込んでくる。小うるさい虫に湯をか
けて退治にかかるが虫も逃げ回り追いかけごっこになる。
 幌加温泉
幌加温泉
層雲峡からロープウェイで黒岳駅へ、更にリフトで黒岳七合目駅へ着くと後
は頂上まで徒歩である。道は険しく汗をかいたが、頂上から眺める雪渓は
素晴らしい。高山植物の花も美しい。

旅行記というのは、何処へ行って、何を食べた、何を見たと書かざるを得
ない。小学生の頃、「どんどん行くと川がありました。橋を越えてまたどんど
ん行くとまた川がありました。河原へ降りてお弁当を食べました。川には小
さなお魚が泳いでいました。」と書いたが、この式のものとあまり変わらない
ものになり易い。旅の印象というものは水にうつる月を拾うのと一緒で、文
章にすると感動がきえてしまい、ただ良かった、美しかったになる。一本の
ポケットウイスキーと一冊の文庫本を持って、車窓からたとえ変哲もない風
景をみるにしろ旅の心を持てば旅の感動がある筈である。食堂車でビール
を飲みながら車窓から外を眺めるとき、生きていることの幸せを感じる、こ
のささやかな楽しみのため旅をしたい。今回、北海道に旅立ったのは、一
週間あまりの休暇と車に乗って見物できる機会を得たのに過ぎない。広い
北海道を一週間くらいで見てまわるには、唯々車を転がして終わるだけに
なるのだが、一つにはかねて行きたいと思った秘湯の二つ、三つを回るこ
と、北海道の海岸線ばかり走ることで岬のいくばくかを訪れることがメイン
テーマだ。最後に、結果的に大雪連峰のうち黒岳頂上に登山できたのは予
想外の収穫であった。
夜の藻岩山から見た札幌は、陳腐な表現ではあるが、宝石箱をぶちまけ
たような光の輝きの中にあった。北の方の光の少ないうす暗いところは北大
のキャンパスらしい。小樽へつづく国道、また中山峠へ向かう国道は、自動
車のヘッドライトの光で帯になっている。
午後三時近く大阪を発って千歳までは空路で二時間足らず。千歳から札
幌まで高速バスで約一時間の道乗りを経て、ここ藻岩山には午後八時過ぎ
に登っている。北海道へは三度目だが、前回来た時には妙な頼まれものを
した。それは、はるか明治の中期、淡路からやって来た「林」という人の先祖
の位牌を古里の菩提寺に届けることである。菩提寺の場所は淡路の慶州
松原の近くらしいが、既に百年近く経っており、寺の名前もわからないので、
位牌の戒名を手掛かりに寺に残っている過去帳と照合する以外には手が
ない。
はるばる北海道から持ち帰った位牌を抱いて淡路に渡ったが、五月の重
くたゆとう空気といっぱいの緑は、数日前に見た北海道の透き通った冷た
い大気と残雪に比べまさに別世界である。
林さんは凡そ百年前、淡路から釧路へ渡ったが、根釧原野の厳しい環境
に耐えられなかった妻は子を連れて林さんの留守の間に古里の神戸へ逃
げ帰ったそうである。その後も林さんは、釧路を離れず孤独の生涯をそこ
で終わったが、残ったものは祖先の位牌と仏像一体だった。
淡路の寺々をさんざんに回って捜し当てられず、諦めかかりながら最後に
行き着いた寺で、寺の奥さんの持ってきた過去帳に尋ね人の戒名を捜し当
てた。
林さんの一族はもうすべて絶えていて、知人宅に残された位牌を寺に納
めることで林さんにまつわることが完結することを意味した。
淡路の寺から見下ろした瀬戸の海は、きらきらと輝いて古里へ帰った林
さんの魂を包みこんだように思ったものである。林さんが、幾十度、幾百度
帰りたいと思った古里との距離が、いまでは何時間かの行程に過ぎない。
いま、サッポロの溢れるような光と、藻岩山展望台の風に吹かれながら
北海道を唯、夏の遊行のひとつにしか考えてないことへの心の痛みを感じ
ていた。
カーブを曲がりきるといきなり交通事故にぶつかった。助手席に寝かされ
た娘さんらしい人の、夏のこととでホットパンツから出た脚には血がしたたり
落ちていて、まるでテレビを見ているようだった。若い娘さん同志で、運転を
していた娘さんはまだ青葉マークで、カーブの曲がり角でふくらましてしまい、
対向車の警笛にビックリして道の左側のブロックべいに衝突したらしい。
助手席の娘さんは、シートベルトをしていなかったのかフロントガラスに顔
をぶつけてガラスで傷を負ったようである。バスタオルで顔をおさえているが
、血に染んでおり、かなりの傷のように見受けられた。
とにかく、ホテルへはいって入浴券を買い、ホテル裏の湖岸へ出ると、だ
だっ広い支笏湖が拡がっている。浜を左に折れてしばらく行くと露天風呂が
ある。
これが目当ての丸駒温泉の露天風呂である。手前は男性用、奥には女性
用としきりがしてある。以前は露天風呂から直接支笏湖が見えたそうだが、
今は柵などがあり(こわれかかっているが)直接は湖を見ることができない。
簡単な脱衣所があり、先着の二、三人が心持ちよさそうに浸っている。
湯は弱食温泉、柔らかい感じで温度も適当であるが、囲みの石がぬるぬ
るしてすべり易い。タオルを頭にのせて浸っていると顔をめがけてアブがう
るさい。
湯からあがって一休みしていると、前の湖を遊覧船が通って皆でこちらを
見ている。隣の女湯の方は遊覧船から見えないようにしているだろうがいさ
さか気になる。
ホテルの一階は食堂になっていて、そこからは支笏湖が見渡すことがで
きる。
気になった事故は、と覗いてみるとようやくパトカーが来て現場検証をして
いる。
運転していた娘さんはハンカチを顔にもっていったりして泣きじゃくってうろ
うろしていたが、やがて警官につかまって事情聴取されている。
再び食堂にとって返して、アイスクリームを食べながら今夜の宿を考えて
みた。
雷電海岸から入りこんだ処に朝日温泉があり、「飢餓海峡」の舞台で知ら
れている。できればそこで宿泊したいものである。
車輪が砂利をはじいて車の底部はガタンガタンと猛烈な音をたてる。雷電
温泉口のバス停から海岸道路を直角に山へ向かうと車幅一杯の砂利道が
続く。途中で、「満員で泊まれません」の看板が出ていたが、構わずにつづら
折りの道を左へ左へと曲がっていくと、いきなり視界に古風な建物が飛び込
んできた。
温泉宿の前庭は、狭くて二台と車を置くには不自由である。横に車をまわ
して空き地にパーキングしてから案内を乞うと宿の老女主人が顔を覗かせ
た。
入湯料を払って早速湯船に飛び込むと、山の湯らしく白濁した湯が疲れた
身体をつつんで快い。湯室の入口は、男女の区別はあるが中は混浴になっ
ている。中は案外広くて、十人くらいは大丈夫である。湯の種類は石こう泉
で、日本では珍しいものといえる。
四方に山が迫っており、日が暮れると寝るしかないこの宿の趣は都会の
俗塵を払うのにはうってつけである。何日か唯湯に入るだけの暮らしがして
みたくなる処である。
もう一度海岸まで出て来た処で今夜の宿を見つけなければならない。ふと
眼の前に民宿の看板が眼についたので、とりあえずそこで泊まることにした。
通された二階から押し寄せる波を見ていると、はるばると来たものだ、と
いう感慨がひとしおである。
宿は女主人ひとりがきりまわしており、冬の内は岩内に戻るそうである。
新聞は一週間まとめて来るとか、テレビはワンチャンネル、それも夜には
いらないとカラーの色がつかないとか、まさに秘境という感じである。
夕食は前の海でとれた昆布、海老、ホッケ、タラなど海の幸を全部ブチ込
んで味噌で味をとった海岸鍋で郷土色満点である。
トランジスターラジオの巨人−大洋戦を聴きながら布団へ横になると、同
時に潮騒も聞こえて旅にいる気分が高揚してくる。
車を駐車場に置いて神威岬へはまず、いきなり丸太でとめた階段をあが
る。しばらくあがっていくと平坦な道がつづく。ゆるやかな下り道から今度は
ゆるやかな上り道にかわるが、あたりは一面草原で陽を避けるものはない。
先端に近くなると道の両方が切りたった崖で危ない処は鉄橋が架けてある。
良い加減くたびれてきた頃に灯台が見えてきた。岬の果てにまだ未練そう
に岩が点々と続いている。一番大きい岩がローソク岩だろう。見渡す限り天
と地と、そして陽光が燦々と輝いている。足元の砂が焼けて熱い。
天空よ カムイ岬の 熱き砂
これから積丹半島をもう一度回って、余市から小樽へ向かう。道は舗装さ
れていて、百キロ近いスピードで走る車の天国であった。
小樽のフッシャーマンズクラブは、岸壁に横付けにされた船のなかにある。
一階は、魚や貝類を一杯置いてある売店、二階が食堂である。メニュー
に中から鮭親子丼を選んだ。
親は鮭、子はスジコで、ご飯にのりをまぶしその上に行儀良く鮭とスジコが
鎮座している。適当な塩加減がご飯と混ざって美味である。
腹加減も良くなったので、車を転がして近くの鰊御殿に向かう。小高い丘
の上にある御殿は、泊村から移築されたものだが、周囲の風景にマッチし
ている。内部は魚具や生活用具が展示され、展示方法としては日本全国変
わりないものだが、唯、やん衆達の寝間の狭さが大きい屋敷と対比して目
立った。経営者がうるおう割りにこうした漁夫達の待遇がどうだったのだろう
か、と思わざるを得ない。
 鰊御殿
鰊御殿
外へ出ると、丘の上から小樽水族館が見える。アザラシが芸をしているの
か、プールの回りに人垣ができていた。
これから再び札幌へ向かうが、途中、有名な小樽の運河へ出た。
この運河も半分は埋め立てられ、それの道路工事の喧噪のなかにあった。
ここも倉敷の美観地区のようにミニチュア化され、観光化されて生き残るの
だろう。周囲に土産物店ができ、団体バスのガイドのマイクがやかましい
内地の風景と同化されるのも近い日のことだろう。札幌、小樽間の高速道路
も素晴らしい。明治の昔小樽から札幌へと開拓の鍬がはいった船山馨の
「石狩平野」の世界と隔世の感というよりも、まるで異次元の世界ともいう
べきである。