 (写真 1)
(写真 1)
日本の3000米峰は中央山岳地帯(北アルプス,南アルプスなど)に有り,且つ1位の富士山を除き,2位の北岳から21位の聖岳までの標高差は僅か179米に過ぎない。 こうしたシチュエーションから比較的容易に全峰を踏破する事ができる。では標高順位に登山のあらましを辿ってみたい。
(標高順位については「山と渓谷社2001山の便利帳」に拠った)
富士山登山(登山日1989・8・12〜15)
(1位 富士山 3776m)
登山を志した人に限らず,日本人の殆どは生涯に一度は富士山に登りたいと思っているに違いない。富士山登山は現在は一般的に5合目から出発しているが,江戸期には富士吉田市の冨士浅間神社から出かけた。浅間神社のご霊水を頂いて出発,馬返しを経て1時間ばかり歩きようやく1合目でガックリ来る。
5合目の佐藤小屋あたりから調子が出て,その後は合目、合目の小屋毎で甘酒,冷やし飴など飲んで,本日の泊まりの本8合の小屋には午後かなり遅く着いた。同行のA夫婦はマラソンもやっていてお二人とも元気一杯だったが6合目あたりで奥さんの調子が悪く本8合の小屋に着いた時は完全に高山病症状になり残念にもご夫婦とも引き返さざるを得なかった。健脚者といえども高山病は油断がならない。小屋はシーズンで登山者が一杯、夜中にトイレへたつ人が寝ている人の手や足を踏んで大騒ぎだった。混んだ小屋ではメガネは必ず外す事が大事だ。翌日は午前2時ごろに出発、夜明けに頂上に到着、幸い日の出は拝めたが摂氏4度の寒さだった。 剣が峰へは一旦奥社へ下りたあとKさんが写真をとってあげると言ったので結局2度登った。
下山は御殿場口コースを取り、7合目からは砂走り登山道を砂まみれで降りた。スピードが出過ぎるので登山道に並んで立つ柱につかまってスピードを緩める始末だった。5合目まで下りて待っているバスに乗り、その日のうちに帰宅した。
風寒くここは富士山剣が峰 幹男
(写真 1)
御殿場口砂走り登山道
白峰三山縦走(登山日 1993・7・28〜8・1)
(2位 北岳 3192m)
(4位 間ノ岳 3189m)
(15位 西農鳥岳 3051m)
第1日目は肩の小屋まで、広河原から大樺沢の流れを見ながら登ってゆくとやがて二股へ着く。ここで分岐しており、一方は八本歯のコルへ雪渓を登り、もう一方はお花畑を見ながら肩の小屋へ向かう。かなりの急坂を過ぎると小太郎尾根に辿り着く。振り向くと甲斐駒ケ岳、また右手にはとてつもなく大きい仙丈ケ岳が聳えている。 肩の小屋から富士山を見ることができる、また目の前には鳳凰三山が展望できる。小屋の近くでキタダケソウを見たがどうも養殖らしい。翌日は北岳を越して農鳥小屋へ、北岳山荘あたりから振り返ってみる北岳は圧巻でよくグラビア写真に撮られている。付近のハクサンイチゲの群落も印象的だ。 中白峰(番外3055m)を過ぎ、やがて間ノ岳へ着くが風が強くて止まっていられない。間ノ岳を下りるとやがて南アルプスらしい小屋の農鳥小屋に着く。翌朝は風が強く西農鳥岳へ向かう登山道では何人かで手をつなぎ烈風に飛ばされないように注意する。頂上からさらに農鳥岳(3026m)を越え、大門沢下降点からは長い降り道になる。早川第一発電所前の開運橋に着けば縦走は終わりになる。
風避けて間ノ岳では昼の飯 幹男
(写真 2)
肩の小屋から見た夜明けの富士
奥穂高岳沢コース(登山日 1994・9・23〜24)
(3位 奥穂高岳 3190m)
(8位涸沢岳 3110m)
(11位 前穂高岳 3090m)
上高地河童橋から10分ぐらい歩くと岳沢登山口に着く。第1日目は岳沢ヒュッテに向かう。岳沢ヒュッテには生ビールがあり堪えられない。翌日は重太郎新道を紀美子平へと、ここで一服してガレ場を前穂高岳頂上へと登る。 頂上でしばらく休んで再び紀美子平へ引き返し吊り尾根を奥穂高へと向かう。
用心しながら歩いてゆくとやがて奥穂高頂上へ着く。目の前のジャンダルムを見るとここを越えて西穂高へ向かうのは第一級のハードだと実感する。
奥穂頂上から白出のコルへ向かうが、穂高岳山荘の眼前の岩場はちょっとしたスリルがある。今日は穂高岳山荘へ泊まるのでビールを飲んだが、お陰でここから20分ぐらいで行ける涸沢岳は断念した。翌日は白出沢を下り白出小屋へ、ここから林道を行けば新穂高温泉である。
瑞々しく生きたし風の穂高岳 幹男
(写真 3)
穂高岳沢コース登山口
穂高連峰縦走(登山日 1995・7・26〜30)
(5位 槍が岳 3180m)
(9位 北穂高岳 3106m)
(10位 大喰岳 3101m)
(12位 中岳 3084m)
(18位 南岳 3033m)
新穂高温泉から蒲田川右俣谷の林道を歩いてゆくと白出沢河原へ突きあたりここから登山道、我々一行は途中の渓流でスイカを食べ、やがて今日の泊まりの槍平小屋に着く。翌日は飛騨乗越まできつい登り、乗越からも急な登り道、槍岳山荘に着くと眼前に頂上がある。 岩場を山頂へ梯子などを使って登ってゆくと憧れの槍が岳頂上に着く。小さな祠が可愛い。ここから北穂高方面を眺めると縦走の闘志が沸いてくる。同じ3000m峰の大喰岳、中岳を過ぎ、南岳を下ると南岳小屋がある。ここから眺める北穂高は屹立していてあそこへ本当に行けるのかと溜息が出そうだ。翌朝大キレットにかかると慎重に進まなければならない。飛騨泣きの悪場をすぎると北穂高の急登になるが、やっと北穂高小屋へ着けば一安心である。ここから南稜を下りて涸沢へ、そして上高地へと向かう。
ガス透けてハクサンイチゲ咲く岩場 幹男
 (写真4)
(写真4)
飛騨乗越から見た槍が岳
荒川三山、赤石岳周遊コース(登山日 1997・8・25〜9・5)
(6位 悪沢岳 3141m)
(7位 赤石岳 3120m)
(12位 荒川中岳 3083m)
今回の登山は前半は爺が岳、鹿島槍へ登り、後半に椹島から荒川三山、赤石岳コースをとった。初日は椹島から千枚小屋への長丁場、ようやく着いた小屋付近の花畑が美しい。
翌日は千枚小屋から悪沢岳、荒川中岳、前岳(番外3068m)を経て荒川小屋で一泊する。このコースは晴天に恵まれ、まさに遊覧コースになった。中高年登山で赤石岳まで足を伸ばさずに荒川小屋で泊まる事にしたので本当にゆっくりコース、悪沢岳の頂上でコーヒーブレイクをして急いでゆく登山者を尻目に遊んでいた。荒川中岳避難小屋で小屋番のおじさんが「大晦日にようこそ」と言ったので聞いてみると小屋は8月31日で閉めるので今日が大晦日だと言う事だった。荒川小屋への急な下りで登山靴がきつくなり足に痛みを覚えた。次の日は赤石岳へ、大聖寺平からしばらく行くと小赤石岳(番外 3081m)に着く。 ここでまたコーヒーブレイク、この日も晴天で絶好の山日和だ。赤石岳頂上は広くあちらこちらをうろうろして時を過ごした後、赤石小屋へ下山した。その翌日も引き続いて下山だけで、途中で聖岳を眺めたりして椹島へ向かった。
ウスユキソウ悪沢岳の岩に咲き 幹男
 (写真 5)
(写真 5)
赤石岳頂上小屋付近
御嶽山登山(登山日 1987・9・12〜13)
(14位 御嶽山 3067m)
田の原から眺めると御岳頂上小屋までほんの一登りと思うがどっこいなかなか着く事は出来ない。しかし信仰の道だけに由緒ありそうな登山道である。
王滝頂上から霊神像を過ぎ、御嶽山神宮奥宮の最高峰である剣が峰までどこが頂上か迷いそうである。さらに飛騨頂上を辿り濁河温泉への下り道となる。
雨に濡れた木道は滑りやすく何度となく転んだ。この山が3000峰登山の1回目だっただけに印象深い。それまでは四国の道を歩き高山は自分の対象外だと思っていただけに登山への奮起を促された事は否めない。
御嶽山登山の水は旨いこと 幹男
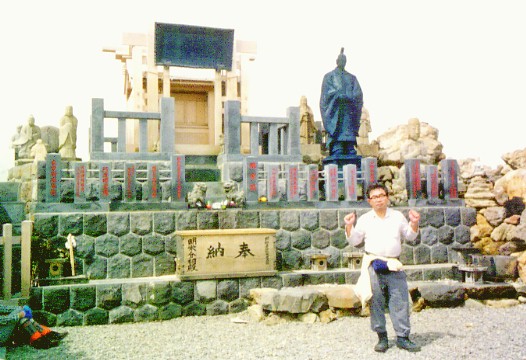 (写真 6)
(写真 6)
御嶽山初めての3000m峰登頂
塩見岳登山(登山日 1997・7・18〜21)
(16位 塩見岳 3047m)
塩見岳へは鳥倉林道のコースをとった。三伏峠まではかなりの急登、小屋で一服して本谷山へ、この山の直前でバテ気味となり、もう登山は止めたと弱音を吐いたが、山頂で一服して立ち直り、塩見小屋まで無事に着く事が出来た。塩見小屋は一杯でテントまで張って収容する始末だった。また、トイレも山道を通っていくと崖っ淵に有り、夜中の暗い中をランプ頼りに行かなければならない。しかし翌日、山頂に登り富士山を見たこと、また登山途中でイワベンケイの群落を見たことは忘れられない。塩見岳は東峰、西峰があり、記念写真も両方撮った。下山は同じ道を通り鳥倉林道に置いてある車へ向かった。
急登を喘げば樹林濃い緑 幹男
(写真 7)
ズングリした入道頭の塩見岳
甲斐駒、仙丈ガ岳コース(登山日 1992・7・23〜26)
(17位 仙丈ガ岳 3033m)
南アルプス林道を通り、北沢峠へ着くとまずは双児岳、駒津峰を経て甲斐駒ケ岳へ登山、長衛荘へ一泊して翌日仙丈が岳へ登るのが一般的なな登山で今回もこの方法をとった。北沢峠から500メートル標高差のある5合目の大滝の頭で登山道は二つに分かれ、一方は藪沢小屋を経て山頂へ行くコース、もう一方は尾根伝いに小仙丈ヶ岳を経て山頂に達するコースである。この時は小仙丈ヶ岳を経るコースをとって往復登山をしたがかなりのアルバイトだったことは間違いない。
登山靴仙丈岳に微風あり 幹男
(写真 8)
仙丈ヶ岳までは一呼吸
乗鞍岳観光登山(登山日 1996・9・1〜5)
(19位 乗鞍岳 3026m)
観光を兼ねて東北の山を楽に登ろうという計画で、磐梯山、安達太良山、一切経山を楽なコースで登った帰りに乗鞍岳に立ち寄った。畳平まで車を入れたので剣が峰までは1時間余りで行ける。コース表では肩の小屋まで30分、其処から剣が峰までは1時間となっている。頂上は一面のガスで寒かった事を覚えている。
山霧の乗鞍岳は摂氏5度 幹男
(写真9)
ガス立ち込めた剣が峰
立山縦走(登山日 1992・8・1〜2)
(20位 大汝山 3015m)
室堂から雄山(3003m)大汝山、富士の折立、真砂岳を経て別山へ、別山乗越から雷鳥沢を下山し雷鳥平へというのが周遊コース。 夏では容易なコースだが10月初旬に吹雪で大量遭難死が有った場所なので油断がならない。室堂から一の越を経て雄山へ、さらに大汝山へと向かったが生憎の雨で大汝休憩所はガスがかかり、レインコートを着込んでも寒い。岩塔を50メートル登った大汝山頂上はガスで展望が効かないので断念、真砂岳を経て内蔵助小屋へ寄った。小屋までは雪渓でロープを張ってあるのが頼りだ。さらに寒くなってセーターを着た。別山で少し遊び、剣御前小屋から雷鳥沢の急坂を下った。付近にはシナノキンバイが一杯咲いていて綺麗だった。雷鳥荘の温泉へ飛び込んで山行は終わった。
すべてガス雄山山頂雨激し 幹男
(写真 10)
立山に咲くハクサンイチゲ
聖岳、光岳縦走(登山日 1998・7・31〜8・7)
(21位 聖岳 3013m)
初日椹島で一泊、翌日に聖沢から聖平小屋へ、ここで泊まり次の日小聖岳を経て聖岳へ向かった。頂上は横殴りの雨で寒く、怱々に再び聖岳小屋へ引き返した。
第三日目は、再び聖平から上河内岳を経て茶臼岳小屋へ向かった。上河内岳では遅れて来たT先生と合流、光岳へ向かうこととした。茶臼岳から易老岳へ、途中でイザルが岳へ寄り光小屋へと進んだ。新設の光小屋は1ヶ月先に完成すると言う事だった。光小屋の夕食にてんぷらと言うご馳走が出たのは印象的だった。光岳から光石へ立ち寄り、これから復路となる。再び茶臼小屋へ立ち寄り、ここから下山、横窪沢小屋で泊まった。翌日、畑薙大吊り橋を通って畑薙第一ダムへ帰り、旅の終わりになった。
横殴りの雨と寒さの聖岳 幹男
(写真 11)
稜線分岐より聖岳遠望
、