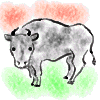
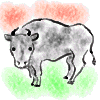
川柳の略歴(二)
前回お話ししたように、前句附は爆発的な人気を呼び、俳諧師にも莫大
な収入をもたらしました。芭蕉はこれを嘆いて、元禄五年二月に、曲水とい
う弟子へ風雅の道をさとした芭蕉三等の文というのを出したほどです。
この前句附の前句が、次第に失われて川柳として独立してくるのですが、
柄井川柳が没して三代まで世襲のかたちで引きつがれた川柳も、四代目は
当時、江戸八丁堀の同人人見周助(眠亭賎丸)に移るとともに、川柳の名前
を離れて「俳風狂句」または「柳風狂句」と称するようになりました。狂句はも
っぱら語呂合わせ、駄洒落に終始しましたので、現在文芸的価値は低くみら
れています。狂句というのは
箱に入れ過ぎて娘を桶に入れ
聟えらびするうち柳臼になり
といった理屈くさい体を借りたもの(注:初めの句は、箱入り娘を大事にし過
ぎて肺病か恋病いで棺桶に入れてしまったという意味。また後の句は、縁遠
い娘が嫁がない間に柳腰からやがて臼腰になってしまったとの意味)また、
掛けことばの句として
よく結えば悪く云われる後家の髪
身ぎれいな後家はかえってぼろを出し
といったものです。
万句合わせのなかの色恋を扱った句は末番句と呼ばれ、これらの句を
抜すいして編集されたのが「誹風末摘花」です。俳諧では、恋句を二句、三
句と連続して並べ、恋の座を形づくるそうですが、これが川柳に影響を与え
たものです。
真実なことゝ
ぜんたいが過ぎると咄す薬とり
(医者へ薬とりにきた下男が、大体主人は房時が過ぎるとむだ口を叩いた
との意味、前句の真実なことゝが効いている)
うろたえにけりゝ
よしねへと前を併せるおちゃぴい
(「おちゃぴい」とはませた女の子。子供と侮っていたずらをしかけると
「つまらないことおよしよ」と大きい声で叫ばれて、うろたえている男を揶揄
している)
などがありますが、風紀上の理由で天保の改革以来、昭和二十五年まで
禁書の扱いを受けています。古川柳の一面がこうした淫靡な笑いを持つの
は、この幕末の時代風景と無縁なものではないのですが、いまは古川柳
研究家は別として、現代川柳に於いては取りあげられておりません。
このように古川柳は狂句となって明治を迎えたわけですが、明治三十年頃
から井上剣花坊、阪井久良伎、岡田三面子といった人達によって新しい
川柳の動きが始まりました。現在の川柳を現代川柳、江戸時代の川柳を
古川柳と今では識別して呼んでいます。ふあうすと川柳社前主幹 故 椙元
紋太さんは川柳明治誕生説を説えて、川柳は明治に始まったと主張してい
ますが、それほど現代川柳は古川柳と離れた存在になっているのは事実
です。
この頃の句として
上酣屋へィゝゝと逆わず 当百
奈良七重ひねもす鐘の鳴る処 水府
大仏の鐘杉をぬけゝ 五葉
などは有名です。
現在続いている川柳の同人誌は大正三年、大阪から岸本水府によって
創刊された「番傘」同九年東京から村田周魚を顧問として出された「川柳
きやり」昭和五年に神戸から椙元紋太を中心に創刊された「ふあうすと」
などをあげることができます。
太平洋戦争に突入する頃から川柳誌も次第に休刊し、昭和十九年には
ほとんど全部休刊してしまいましたが、戦後を迎えるとともに川柳活動は活
発となり、現在の隆盛をみるに至りました。戦後は特に女性作家の台頭が
著しく大きい特色になっています。
これで川柳の歴史は終わりまして、次回からは「川柳の笑い」を述べたい
と思います。