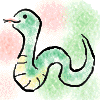
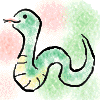
川柳の作り方(二)
今回は実際に作句の添削をしてみたいと思います。次の句は老人川柳
会の初心者がつくられたの評して添削してみたものですから参考にして下
さい。
(原句)コオロギの鳴く声聞きて秋感じ
思ったままを云うと川柳になると簡単に云いますが中々そうはいきませ
ん。この句の欠点は下五の念押しというところです。コオロギの鳴く声を聞
くといえば秋を感じているわけですからもう一度「秋感じ」という必要はあり
ません。読者に句を見て秋を感じてもらおうというのが作句のコツです。ま
た、川柳はできるだけ口語を使うことが望ましいので「聞きて」は「聞いて」
とすべきです。
(添削)コオロギを聞いて祭りの晴れ着縫う
(原句)鐘太鼓浮かれて騒ぐ村祭り
この句も前の句と同様に鐘太鼓といえば、浮かれて騒ぐということを連想さ
せるし、また村祭りということも連想させます。鐘太鼓の祭ばやしを聴いて別
のことを思うことが大切です。例えば鐘太鼓を聴きながら祭の支度をしてい
るという情景はどうでしょう。
(添削)鐘太鼓祭り仕度をせかされる
(原句)美しきガイドのありて旅楽し
これでは作者の感想と終わってしまいます。美しいガイドが居てという所
で旅が楽しかっただろうと連想させますので、云わずもがなというところで
す。川柳には発見の楽しみというのがありますが、もしガイドさんが歌手に
でも似ていたらどうでしょう。団体のたびの楽しさがきっと倍加すると思い
ます。
(添削)二号車は都はるみに似たガイド
(原句)秋の旅歓声ごとにバス止まり
この句の言わんとするところはわかりますが言葉が整理されてないので
句にぎくしゃくとしたものを感じます。渓谷を通る観光バスが紅葉した景観を
眺めるごとに歓声を挙げるというようにして次のようにしたらどうでしょう。
(添削)紅葉へ歓声あげるバスの旅
(原句)洗い髪虫鳴く庭に佇みて
この句は風呂で髪を洗ったまま庭に出て虫の音を聴くということですが、
これではすっきりしません。上五の洗い髪を思い切って下五へ持ってきて
次のようにすると句が安定します。
(添削)虫の鳴く庭に佇む洗い髪
(原句)虫の音遠くになりぬ犬の吠え
情緒としてこの句もわかりますが、やはりかたちが整ってないと思います。
すっきりしたかたちにするとすれば次のようになります。
(添削)遠吠えの犬に鳴きやむ庭の虫
(原句)奥道後展望台に秋の鹿
作者が奥道後に行って実際にけんぶんしたことをそのまま作っているの
で、日記の最後に書き添えるとすればこのままで良いのですが、一般の鑑
賞に供するとすれば上五はもっと情緒があってよいわけで、奥道後にこだ
わる必要はありません。
(添削)小雨降る展望台に秋の鹿
(原句)石手寺に一つ打ちたり秋の鐘
(原句)民宿へ秋を探しにきたおんな
二句を一度にもってきたのは、この二句の想いを取捨選択すれば、もっ
と良い句になるからです。添削の句は子規の「柿食えば鐘が鳴るなり法隆
寺」に似てしまいましたが、また別の趣もあって私はかまわないと思います。
(添削)石手寺で秋を探せば鐘がなり